ヴィウの囁きと美しき挑戦。
シーズン1 始まりのささやき
エピソード3〈見つからない探し物〉
展示会まで、もう指で数えられるほどの日数しか残っていなかった。
立て直した企画の資料を詰め直し、数字を入れ替え、想定問答を並べる。
部長の厳しい眼差し、スタッフの期待に満ちた声が頭を離れなかった。
会議室を出ると、壁のカレンダーの赤丸だけがやけに目に刺さった。
*
夜。オフィスの灯りはだいぶ減っていた。
デスクの上を片づけ、PCを落としてから、ふと視線を横にやると、祐輔が端末に齧りついていた。眉間に皺を寄せ、画面を凝視している。
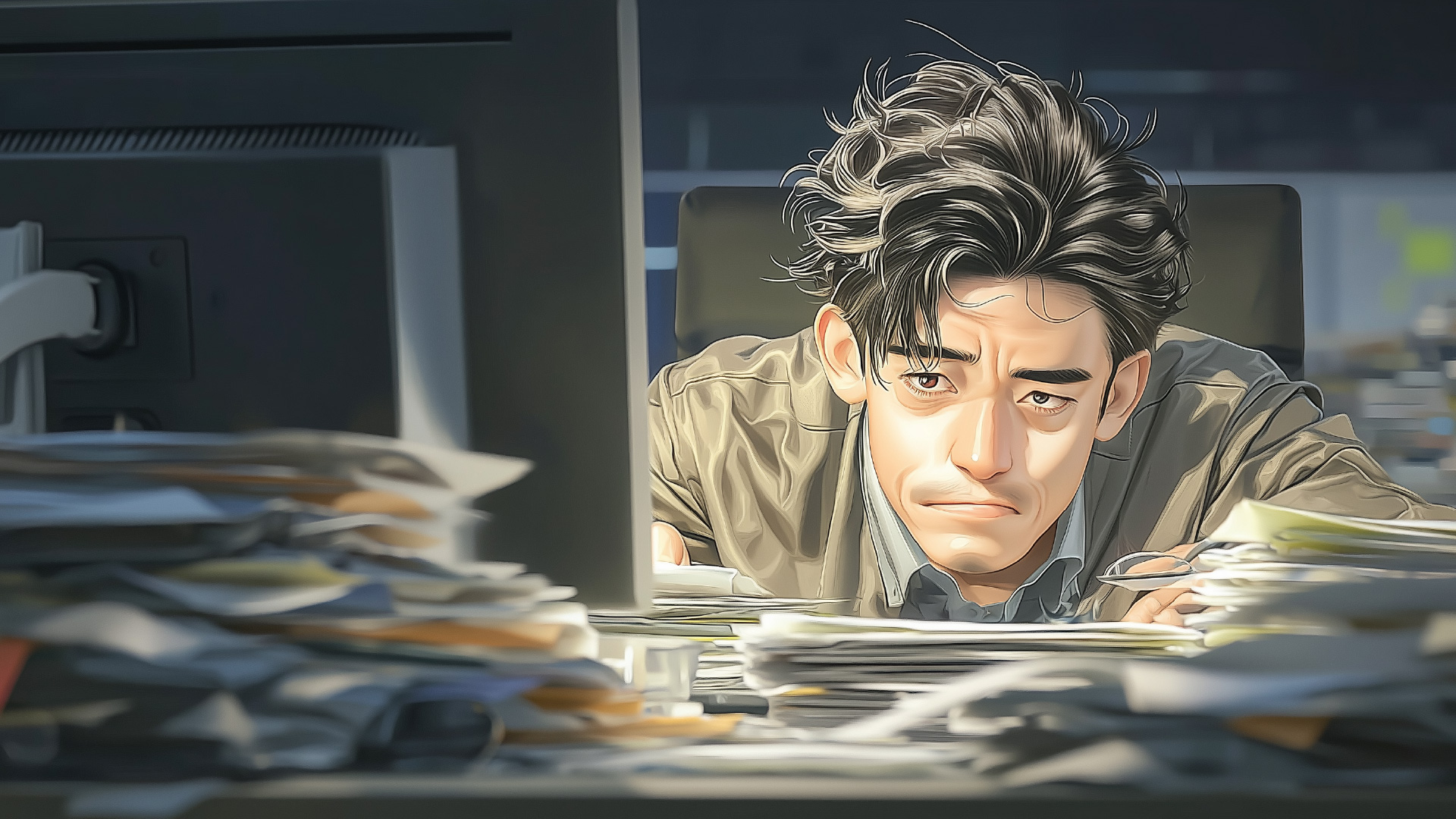
「祐輔くん、何かわかった?」
「はい。
いえ、どこがどうだってことじゃないんですけど……」
顔を上げ、少し照れたように笑った。
「あ、チーフ、お帰りですか?」
「今日はもうおしまい。
祐輔くんも毎日遅いんだから、たまには早めに、って、もう遅いけど……もう、しまったら?」
「はい、ありがとうございます。
もう少しだけ見て、帰ります!」
奈緒美は、祐輔の見送りの声を背中で受けながらエレベーターに乗った。
時計は、夜の十一時に近かった。
*
玄関を開けると、家は暗い。
リビングのテーブルには、子どもたちのプリント、食べかけのパン、健一の読みかけの新聞が残っている。
テレビのランプが点いたまま、部屋は静かだった。
静まり返った空気は昼間の熱を失い、冷え切っている。家族の気配は跡形もなく消えていた。
片づけようかと一瞬思ったが、手が動かなかった。
ソファに体を沈める。天井の明かりが滲み、視界がゆっくりと落ちていった。

*
昼休み、カフェ・セレニタの窓際で、ゆう子が手を振っていた。
黄色い壁に緑の窓枠、深煎りの香りがふんわり漂う、なんとなく落ち着く席だ。
ゆう子に遅れて席についた奈緒美は、いつものように他愛もない話題が続くと思っていたが、今日は少し様子が違った。
「最近、娘が反抗期でね。
家のことも心配で…」
突然、ゆう子が家族の話を始めた。奈緒美は、少し驚いた。シングルマザーである彼女が普段は口にしないことを、今日はやけに熱心に話している。

「萌音ちゃん、中二だっけ?
愛莉と一つ違いよね」
「そう。
学区は違うけど、LINEでよくやり取りしてるみたい」
(どうして急にこんな話をしてるんだろう?)
奈緒美はそう思いながら、相槌を打つが、どこかふわふわとした感覚が続いていた。ゆう子の言葉が妙に遠くに感じられ、何かがいつもと違うような気がしたが、深く考える余裕もなかった。
突然、ゆう子のスマホが鳴る。
「あ、部長からだ。
ごめんね、奈緒美。
先に戻るね」
ゆう子はそそくさとその場を去り、奈緒美は一人取り残された。
さっきまで会話していた姿勢のまま、しばらくぼんやりとテーブルを見つめていた。
(そういえば、ヴィウって一体何だろう?
新しい何かのブランドかしら……)
ふと思い立って街を歩き始めた。

*
渋谷の雑踏を抜け、スクランブルの人波を横切る。
初冬の昼下がりの陽射しは暖かく、アスファルトの照り返しが眩しい。
青山の裏通りでは、午後の光が傾きはじめ、ガラス越しに並ぶ器が柔らかい光を反射していた。
銀座の大通りは、夕方のオレンジに染まり、ショーウィンドウに人の影が長く映っている。
それでも「ヴィウ」の文字はどこにもなかった。
検索にも出てこない。
SNSを覗いても、それらしい口コミすら一つなかった。
どの看板にも見当たらない。
時計を見ると、もう夕暮れの時刻。足取りは自然と速くなる。

六本木の通りでは、街の灯が次々と点りはじめ、昼の喧騒が夜の顔に切り替わっていく。
探しても探しても見つからない。焦燥だけが足を速める。
やがて渋谷に戻る坂道。
通い慣れたはずの街なのに、空気だけが少し入れ替わったように感じた。
坂の突き当たりに、見慣れない町屋がぽつりと佇んでいた。その先は空が広がり、眼下には、坂の下に広がる渋谷のビル群の灯りが瞬いている。
町屋の庭の奥から石段が下へと続き、古い小路に降りられるようだ。

低い軒先に小さな灯りがともり、生成りの布の長い暖簾が揺れている。
暖簾の横には短冊が一枚、風に揺れていた。
〈ヴィウの囁きに耳を傾けて〉
胸が高鳴る。
「見つけた……!」
思わず声をあげた。
奈緒美は指先で暖簾に触れた。
呼吸をひとつ整え、布を押し分けて奥を覗き込む。

誰かの気配があった。
声をかけようと、息を吸った──
その瞬間、目が覚めた。
夢だった。
ソファに横たわっていた身体を起こすと、手元でスマホが震えている。
画面には「北川祐輔」の文字。
彼はまだ、会社で残業していたのだ。
「チーフ!
こんな時間にすみません!
大変です!」
夢の余韻は、一瞬で現実の危機にかき消された。


