ヴィウの囁きと美しき挑戦。
シーズン1 始まりのささやき
エピソード8〈揺るぎない結果〉
――奈緒美が京都から帰った翌日。
高埜木魂から渡された原料と資料を胸に、会社のオフィスへと向かった。
開発フロアのドアが開いた。
「チーフ、おかえりなさい!」
立ち上がった祐輔の声が、ワンフロアの空気をやわらかく揺らす。振り向いたメンバーの目に、ほんのわずかだが光が戻っていた。
奈緒美は深呼吸をして、抱えていたアルミ缶をそっと机の上に置いた。

「これが……新しい原料よ。
オリーブの粉末。
資料も一緒に確認して」
彼女は高埜木魂から受け取った紙の束を差し出し、祐輔の方へ向き直る。
「この資料、PDFにして複製を保管しておいて。
原本は研究室に渡すから。
版管理、あなたのリポジトリにも残して」
「了解です!」
短く頷き合い、奈緒美は缶と原本を抱え直した。
研究室へ向かう通路は、朝の光が斜めに差し、床の白を一段明るく見せていた。
京都から帰ってからの奈緒美には、同じフロアでも空気は別物だった。暗闇の底で手探りだった頃とは違う――そんな感覚を、歩幅のリズムが教えてくれる。
*
研究室の自動ドアが開く。白い匂いがする。
「お疲れさまです」
白衣の研究員が振り向く。無言の視線がアルミ缶へ吸い寄せられた。
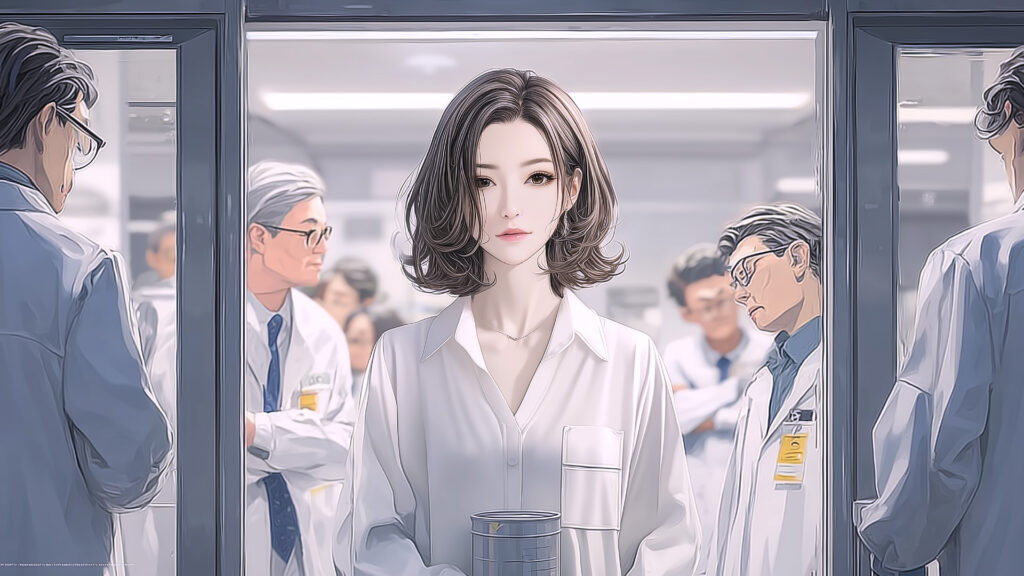
奈緒美は缶を開け、さらに内袋のアルミパックを取り出す。
「高埜さんから。
オリーブの粉末です。
原本の資料、テクニカル編は巻末に」
研究員のひとりがパックを受け取って透かすように見た。
「……なんだこれ?」
袋口を指でつまみ、乾いた手つきで軽く振る。
「フリーズドライ加工?
大袈裟な」
その声には、技術の正しさを認めつつも、どこか鼻で笑う響きが混じっていた。
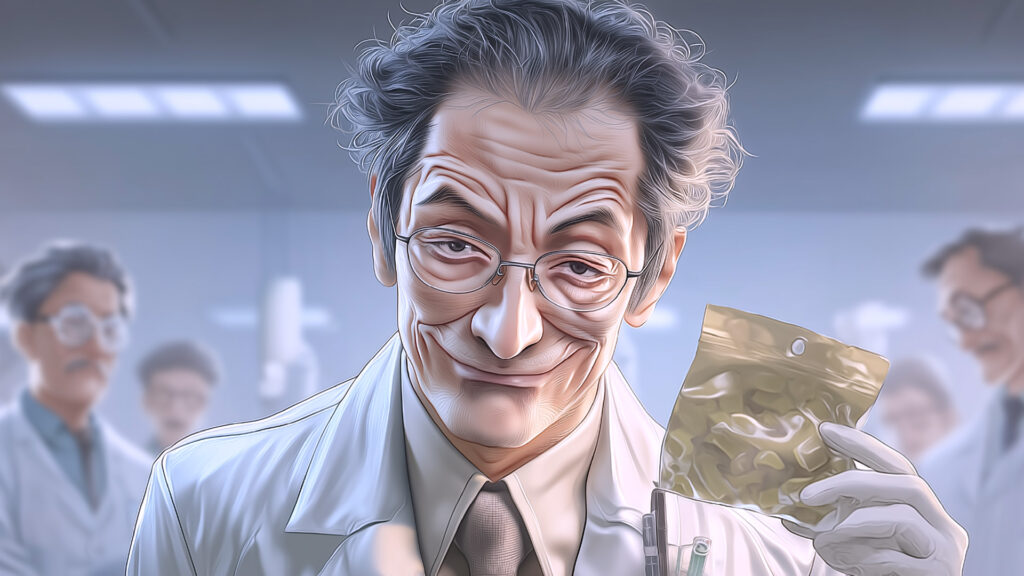
奈緒美は、言葉を飲み込んで小さく頷いた。
(大袈裟かどうかは、結果が答える)
胸の奥で小さな火花が散る。だが今は、火花よりも進行表だ。彼女は手短に要件を伝え、発酵の準備を依頼した。
「培養槽は3系統で。
温度・湿度のレンジはこれ。
試料の記録は写真も残して」
研究員たちは手際よく動き出し、パラメータがモニターに並ぶ。
防塵ガラス越しに、粉末が慎重に投入されていく。計器は落ち着いた数値を示し、緑のランプがぽつりと点った。
安堵が広がる。
(よかった……これで間に合う)
奈緒美の胸にも、ようやく呼吸が満ちた。
*
二日が過ぎた。展示会まで、残り二日。
研究室には、張り詰めた静けさが戻っていた。測定の時刻が近い。
テーブルの角に置かれた紙コップの水は、もうぬるい。時計の針は音を立てないのに、焦りの音だけが耳の奥で鳴っている。
「測定、始めます」
研究員の声。
試験機のランプが点滅し、インジケーターが滑るように動いた。紙がプリンタから吐き出される。白の帯にインクの線が走って止まる。
研究員が目を落とし、固まった。
「……ゼロです」
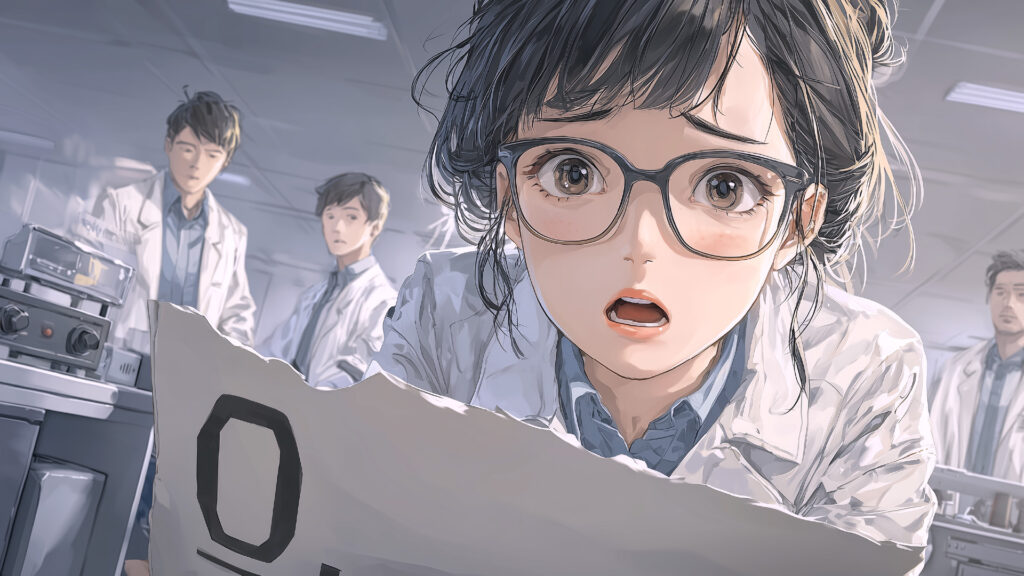
誰かが息を飲む音が、やけに大きく響いた。
奈緒美の視界の縁が静かに暗くなり、床に微かな揺れを感じる。
発酵の手順は踏んだ。見た目も匂いも、進んでいるように見えたのに――結果は空虚だった。
「そんな……」
声が擦れ、すぐ空気に吸い込まれた。
「やっぱり効かないじゃないか」
「見た目に騙されただけだ」
諦めと冷笑の混ざった声が、静かな実験室の壁を回って戻ってくる。
今朝までの安堵感は、まるで嘘だったかのように消えた。
奈緒美は机に手を置き、指先の感覚を取り戻そうとした。
(どこかを間違えた?
どこ?)
頭の中でチェックリストが高速で走る。だが答えに触れる前に、心臓だけが早鐘を打った。
そのとき、祐輔が顔を上げた。

まっすぐこちらを見るわけではないのに、視線に光が走った。
何も言わず、椅子を押しのけて立ち上がると、足早に研究室を出ていく。ドアの閉まる音がいつもより大きい。
何秒、何十秒だったのか、時間の輪郭が萎む。
奈緒美は追いかけず、ただ胸の前で指を組み替えた。鼓動の数を数える以外、今できることが見当たらない。
*
数分後。
祐輔はノートパソコンを抱えて戻ってきた。
額にうっすら汗を浮かべたまま、近くの台に置く。指がタッチパッドを滑り、ファイル名の一覧が呼び出される。

「これ、見てください」
モニターには、複製保管しておいたテクニカル編のPDF。
スクロールバーが進み、あるページで止まる。
満月のイラストと、赤い強調線が目に飛び込んだ。
──粉末は必ず満月の日に発酵させること。
沈黙が落ちた。
研究員の一人が眉をひそめる。
「満月の日?
タイミングで結果が変わる?
馬鹿な」
もう一人が唇だけ笑って肩をすくめた。
「オカルトだろ。
そんなことで再現性が左右されるなら科学じゃない」
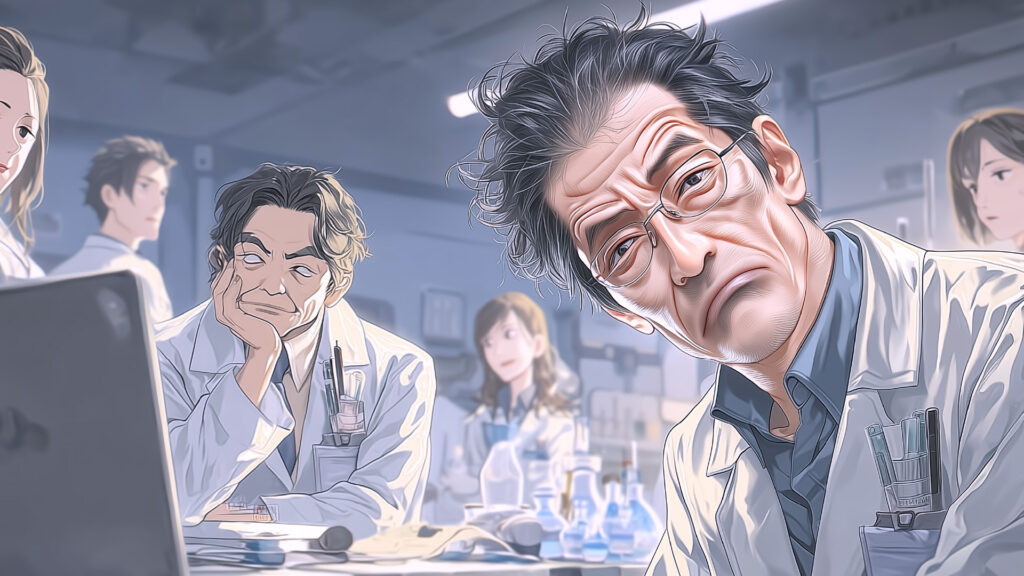
「でも!」
祐輔は声を張る。
「今回、満月じゃない日に仕込んだんです。
効果ゼロの理由、これしか――」
最後まで言い切る前に、鼻で笑う音が遮った。
「満月の夜にドラマティックに、って話は理解できるよ。
発表用の演出なら上出来だ。
でもデータはゼロだ。
現実を見よう」
空気が重たく沈む。
祐輔は唇を噛んで画面から目を離さなかった。
奈緒美は青ざめたまま、研究室の白さが遠のくのを感じていた。
彼らの言葉は、鋭く胸に刺さった。
けれど、抜く力がもう残っていなかった。
(ここまでやってきたのに……あの光は幻?)
喉が熱くなるのに、目は乾いている。泣く余裕がない、というのはこういうことだろう。

視界の端で、曇った窓の外を雲が流れていく。
光は隠れている。
その曇り空を見つめたまま、京都での高埜木魂の声が、ふいに鮮明に甦った。
――自然のリズムを無視したら、力は宿らへん。
たった一言。
あのときは、たぶん比喩だと、どこかで思っていた。
だが今、胸の一番痛む場所に、ぴたりと収まって離れない。
奈緒美はポケットからスマホを取り出した。
指先がわずかに震える。連絡先の一覧に“高埜木魂”の文字がある。
開発フロアの空気、研究室の冷笑、発表までの残り時間――すべてを一瞬だけ遠くに置いて、通話ボタンを押した。

呼び出し音が、心臓の鼓動と重なって響いた。
白い研究室の空気は冷たいまま。
ただ、その音だけが未来へ続いていた。

