ヴィウの囁きと美しき挑戦。
シーズン1 始まりのささやき
エピソード13〈美しき挑戦〉
展示会から数週間が経った。
熱気は遠のき、会社にはゆるやかな日常が戻っていた。
展示会の残務処理も終わり、特別プロジェクトは解散し、メンバーはそれぞれの部署に散っていく。
廊下ですれ違う顔に疲労の色はもう、消えていた。代わりに目の奥に確かな誇りが宿っていた。

メールボックスには、来場者からのメッセージが毎朝のように届く。
〈あの一滴、忘れられません〉
〈自然と科学がつながった感覚がした〉
文章の端々に震えのような熱が残っていて、読み終えるたびに胸が少し温かくなる。数字よりも、こういう声の方がずっと重い。奈緒美はそう思った。
会議室の窓辺に立つと、壁に立てかけたパネルが光を返す。
展示会で使ったポスターの一枚。銀色の葉を透かす木漏れ日の写真は、今見ても息をのむほど静かだ。喧騒の中でこそ際立った“静けさの演出”。その効きを、奈緒美自身が一番よく覚えている。
ブランド開発部のフロアでは、新しいルーティンが始まりつつあった。
「チーフ。
これからも、よろしくお願いします!」

祐輔が軽く頭を下げる。営業からブランド開発部へ――本人の強い希望と奈緒美の口添えで、正式に異動が決まったのだ。
真新しいデスクには、市場資料とデザイン案が積まれている。角の少し曲がった見本ラベルを手に取りながら、彼は不慣れな笑みを浮かべた。けれど、その瞳は期待でまっすぐだ。
午後の打ち合わせが終わる頃、祐輔がふいに口を開く。
「そういえば……
奈緒美さんって、スキンケアはやらないって聞いたんですけど、どうしてなんですか?」
不意を突かれて、言葉が喉で止まった。
彼は続ける。
「うちの会社って、スキンケアの案件、けっこう多いじゃないですか。
僕なんかが言うのもなんですけど……チーフは最高の適任者だと思うんです」
奈緒美は少し驚いて彼の顔を見た。年下の部下の率直な思い。その素直さが、胸の奥にじんわりと染み込んでいく。
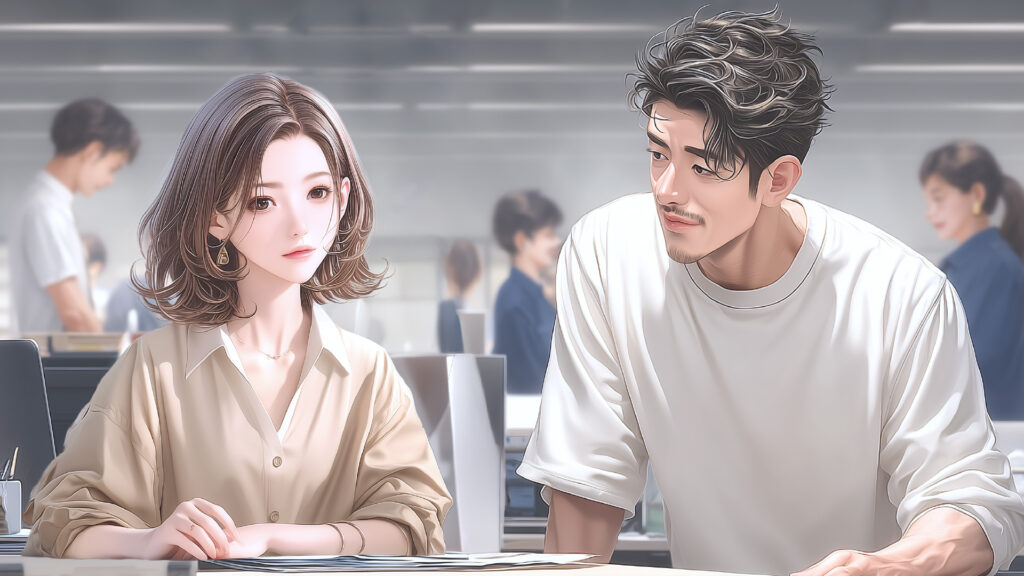
「それに、化粧品って、他の製品に比べてもデザインの比重が大きいですよね。
パッケージとか、ブランドの世界観とか。そういうところも面白そうだなって。
僕、学生の頃は、ちょっとデザイナーに憧れてたんです」
「あ、そろそろデータ計算終わってる頃かな。
ちょっと見てきますね」
と言いながら、祐輔は自分のデスクに戻って行った。
*
(スキンケア。
これまでずっと避けてきた分野。)
胸の奥で小さな棘が動く。
スキンケア。
あまりにも、自分に近すぎる。
だから、これまでずっと避けてきた。

手を伸ばした瞬間、何かを突きつけられる気がする。
試されるのは、知識でも、技術でもない。
自分自身——そのものだ。
*
夕方、部長に展示会後のレポートを提出すると、短い言葉が返ってきた。
「よくやった。
次は“継続”だ。
点を線にしていこう」
奈緒美は会釈し、ドアを閉めて深く息を吐いた。
*
夜。
子どもたちが眠りにつき、家の音が静まる。洗面台の前に立ち、ヴィウクリームの蓋をひねった。
白檀のやわらかな香りが立ちのぼり、張りつめていた神経が少しずつほどけていく。指先で少し取り、頬に触れる。しっとりとした感触が体温でほどけ、肌に寄り添いながら沈んでいく。
(この瞬間に、何度も助けられてきた)
鏡の中の表情は、少し前とは全然違う。
「ここまで支えてくれたのは、このクリームだった。
肌も、そして心も――」
自分にだけ聞こえるほどの小さな声で呟く。
肌の弾力や輪郭の変化はもちろんある。けれどそれ以上に、気持ちの揺れが整う。ざわめきが収まり、呼吸が深くなる。

(これは、ただのスキンケアじゃない。
私にとって“還るところ”となりつつあるわ)
クリームの名――ヴィウ。生命の声。
まるで、耳元で囁くような、その言葉が、あの日から胸の底で微かな響きを持ち続けている。
ソファに腰を下ろし、ぼんやりとカーテンの隙間から覗く月を眺める。満月だった。
あれからちょうど一ヶ月。ずっと変わらぬ自然の営みが、知らないうちに全てを支えてくれている。心の底から感謝の気持ちが湧き上がってきた。
その時、スマホが震えた。
画面には「高埜木魂」の文字。
――奈緒美さん、この度のプロジェクト、お見事でした。
実は、一つお願いしたいことがあります。
『ヴィウ』のブランド構築に協力していただけないでしょうか?
そのメッセージを見た瞬間、奈緒美の心は大きく揺れ動いた。
ヴィウ――今や彼女の日常に欠かせない存在となったこのクリームのブランドを、自らの手で構築するというオファー。それは、彼女にとって新たな挑戦であり、同時に避けられない決断を迫られるものでもあった。
(ヴィウブランドを……私が?)
心臓が、胸の内壁を静かに叩く。
驚きと期待が交差する中、奈緒美は自分自身に問いかけた。これまでヴィウに救われてきた自分が、今度はそのブランドを創り上げる立場になる。それは非常に魅力的で、同時に恐ろしいほどのプレッシャーでもあった。

奈緒美は、鏡の前に立ち、ヴィウクリームを改めて手に取った。今や彼女にとって、このクリームはただのスキンケアアイテムではなく、自信を与え、心の支えとなる存在だった。
「このクリームがなかったら、私はどうなっていたんだろう…?」
そんな思いが頭をよぎる。ヴィウに頼ることで、彼女は再び輝きを取り戻した。だが、その一方で、心の中にふとした不安が広がっていた。それはヴィウへの依存ではなく、高埜木魂への思いが少しずつ心に芽生えていることに気づいたからだった。
彼の優しさ、神秘的な魅力、そしてプロフェッショナルな姿勢――奈緒美は気づかぬうちに彼に惹かれていた。しかし、家族との安定した生活の中で、この感情をどう処理すべきか分からなかった。
高埜木魂からのオファーを受け入れるか否か、奈緒美の心は揺れていた。家族との生活を守りながら、新たな挑戦に向かうことができるのか? そして、尊敬とも憧れともつかない感情が、胸の奥に静かに膨らんでいることを、奈緒美は自覚していた。
――心の中に浮かぶ輪郭のないものに、どう触れればいいのか。
そのまま、ただ静かに見つめるしかなかった。

キッチンのカウンターには、展示会場の控室で配られたミネラルウォーターのボトルがまだ一本残っている。子どもたちの描いた絵がマグネットで貼られ、冷蔵庫の横には以前のポスターの小さなカンプが立てかけてある。
奈緒美は静かにスマホを手に取り、深呼吸をした。本当にこの道でいいのか?
スマホを持つ手の指が、一瞬、震えた。
あまりにも身近すぎるがゆえに、これまで避けてきた分野
――スキンケアのブランド構築。
それは、彼女自身のすべてが試され、曝け出されるような恐怖と、武者震いするほどの高揚感が同時に渦巻く感覚。
高埜木魂。
名を思うだけで、胸の奥がわずかにざわめく。
それが何かは、まだ名づけられない。
決断する奈緒美の心の中に、すべての想いを超えてある言葉が浮かんだ…。
~美しき挑戦~
新たな未来への扉が少しずつ開かれていることを感じながら、奈緒美は高埜木魂へメッセージを送った。

「喜んでお受けいたします☺️」
新たなチャレンジとともに、奈緒美は次のステップへと進もうとしていた。
*
翌朝、ブランド開発部のフロアはいつもより早く灯りが点いた。
机の上に置いた新しいノートの1ページ目。
見出しをひとつ書く。
――viw / Brand Notes
横に小さく線を引き、次の行に、昨夜の言葉をもう一度。
「美しき挑戦」
ペン先が紙をなぞる感触が、はじまりの印に思えた。
廊下の先で、祐輔の軽い足音が近づいてくる。
「おはようございます、チーフ」
「おはよう。
今日から、いくよ!」
奈緒美は顔を上げて微笑んだ。
満ちていく途中の月のように、まだ完全ではなくていい。
大切なのは、歩き出すこと。
変わらないものに支えられながら、新しい光へ向かって。

*
シーズン1終わり
シーズン2 へ続く
著者|游水(Yusui)
挿絵|Midjourney(AI生成ビジュアル/アートディレクション:Beauty Saga Studio)
制作・編集|Beauty Saga Studio
運営・発行|株式会社リーズンラボ(Reason Lab Inc.)
Special Thanks|LBH Corp.
原料およびバルク製造での技術協力により、
この物語に「手ざわり」と「香り」を与えてくださいました。
© 2025 Beauty Saga Studio / Reason Lab Inc. All rights reserved.
物語が、現実を生み出す瞬間に。— ビューティサーガスタジオ
※本サーガに登場する製品は、実在する開発背景および製造販売業の許可に基づいて構成されています。

