肌の精霊と対話する。
シーズン1 月落ちの刻 ~ビワの精霊の物語~
プロローグ〈神の視界(Visione)〉
高埜木魂(たかの・こだま)──令和の化粧師。
代々続く化粧師(けわいし)の家系に生まれた彼は、受け継がれた技術の重みを誰よりも知っていた。
絢爛たる伝統の中で育ち、その価値を守り続ける覚悟と、ただ守るだけでは生き残れない現実とのあいだで、彼の心は揺れていた。
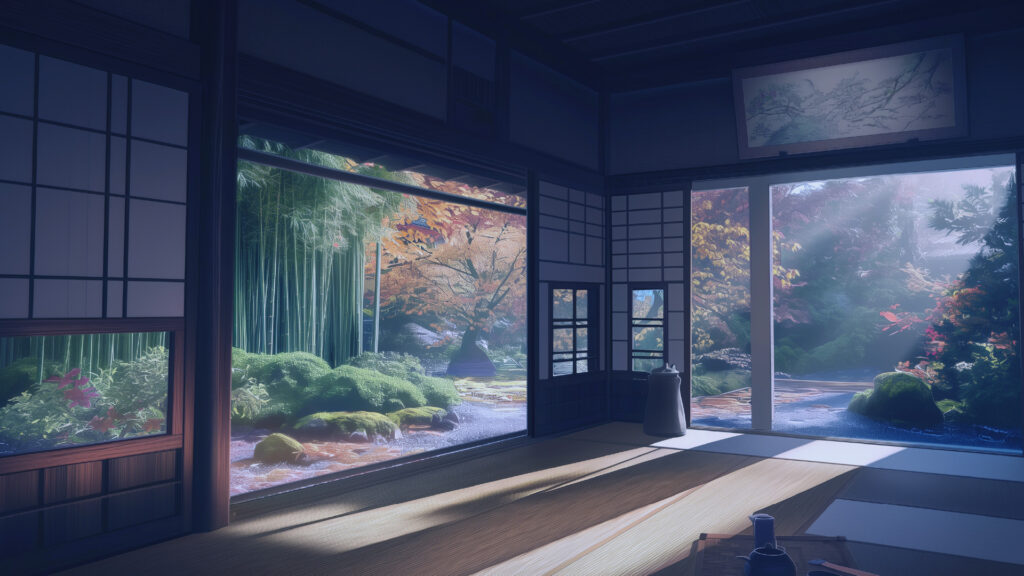
「変えざるものと、変えるべきもの」
──その言葉は、かつてある人物からかけられた問いだった。
高埜木魂は、そのひと言を今も胸の奥深くに刻んでいる。
彼の使命は、ただの継承者で終わらない。
古の技に現代の息吹を与え、「美」という概念そのものを新たに創り上げること。
それが、彼の歩む「化粧道」だった。
*
秋の終わり。
高埜木魂は、京都・愛宕山のふもとにある古刹を訪れていた。
寺に併設された小さな茶室。縁側の障子をすこしだけ開け、朝の空気を取り込んだその室内で、彼は静かに座していた。

目を閉じ、呼吸を整える。
全身の気配を外界にゆだねながら、意識の縁をゆっくりほどいていく。
──その時だった。
眉間の奥がふいに熱を帯び、意識の底からじわりと何かがせり上がってきた。
視界が、変わった。
目を開けた瞬間──
目の前にいた人物の“肌”が、突如、世界の中心に飛び込んできた。
乾燥の兆し。皮膚温の偏り。真皮の線維の乱れ。
それは、表層ではない。
肌の奥の奥──“揺らぎ”や“迷い”といった、心の振動が伝わってくるようだった。
理屈でも、経験でもない。
それはまさに、「視界」としか言いようのない異変。
高埜木魂は直感する。
──肌が語りかけてきている。
しかもそれは、今ある状態や美の衰えだけではない。
その奥に、まだ言葉にもなっていない“未来への意志”すらも帯びていた。
これが、彼に初めて宿った異能。
神の視界(Visione)。
それは静かに、だが確かに彼の中に根を張り始めた。

以後、高埜木魂が肌に触れるとき──
そこには「見た目」だけではない、奥にある“理由”が、
まるで呼吸のように伝わってくるようになった。
なぜ、そうなっているのか。
どうすれば、戻れるのか。
それを、肌のひとえの膜が、そっと語ってくれるようになった。
*
だが、この視界は代償とともにあった。
この力を使うたびに、高埜木魂の内側から何かが削れていく。
深く吸い込んだ息は、どこにも届かないまま熱に変わり、ゆっくりと失われていく。
呼吸は浅く、血の巡りは鈍くなり、骨の芯まで冷たくなる。
それはまるで、他者の“美”を受け取る代わりに、自分の美を手放していくような感覚だった。
──それでも、彼はこの力を受け入れた。
それこそが、化粧師としての応答であると信じていたから。
肌の奥にある、まだ言葉にならない“何か”。
それに静かに耳を澄ませ、見えない答えを共に探す──
その行為こそが、彼にとっての「化粧」だった。
縁側に腰を下ろし、静かに息を吐いた高埜木魂は、首から提げていた小瓶をそっと取り出した。

止水(しすい)。
化粧師にのみ現れる、“色と気配”を宿した液体。
高埜木魂の 止水 は、「赤」。
火とも血とも異なる、それでも確かに“生きた赤”だった。
その止水が、小瓶の中で──ふわりと揺れた。
なにかが、目に見えぬ手で触れたような気配。
*
──その瞬間、スマートフォンが震えた。
画面に表示された名前は「美咲」。
東京でサロンを営む、古い友人であり、かつて研究を共にした美の同志──
そして、今でもどこか彼を特別に思い続けている女性だった。

「……木魂さん、お願い。
最近、お客さんの肌に、急に赤みやぶつぶつが出るようになって……
どんな施術をしても逆に悪化するの。
こっちの手を、拒んでるみたいで……」
美咲の声は、いつになく不安定だった。
その切実な訴えは、高埜木魂の“視界”に、すぐさま異変の気配を落とした。
それは、単なる施術のミスでも、処方や機器のトラブルでもない──
少なくとも、そういった“普通の不調”では片づけられない何かが、肌の奥で、静かにうごめいている気がした。
「……わかった。
すぐに行く」
彼は電話を切り、止水の状態を確かめるように小瓶を握りしめ、ゆっくりと立ち上がった。
庭の竹が、ひとつだけ、細く鳴った。
高埜木魂の視界は、静かに、次なる変化へと開かれていく。
──その気配が、どこから届いたものなのかを知るのは、もう少し先のことになる。


