肌の精霊と対話する。
シーズン1 月落ちの刻 ~ビワの精霊の物語~
エピソード10〈命キレイ〉
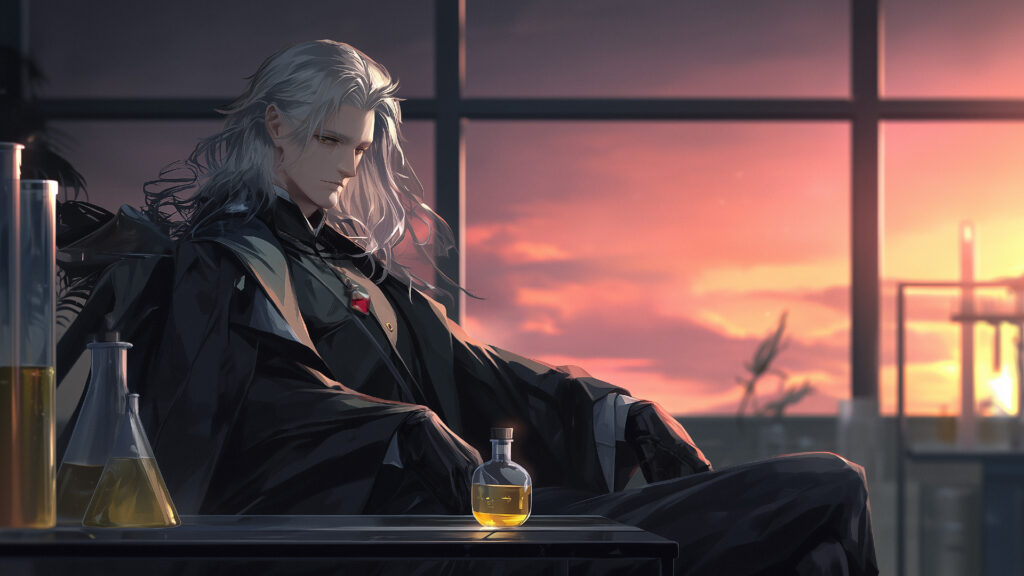
ビワの発酵研究は、1ヶ月にわたる高埜木魂の緻密な努力の末、
ついにその成果を見せ始めた。
「月落ちの刻、自らの床で。」
精霊が囁いたその言葉。
自然が与えた条件を忠実に再現した結果、奇跡のような発酵液が静かに立ち上がった。
金色に澄んだ液体は、わずかに揺れるだけで、かすかな香気を放つ。
その香りは、ただの芳香ではなく、何かに“応えている”ような深さを帯びていた。
「……これで、やっとや」
高埜木魂は静かに呟き、研究室の静寂の中で深く息をついた。
量産化の道も見え、美咲のサロン「花影」の未来にも確かな光が差していた。
このひと月、張り詰めていた心がようやく、少しだけ緩んでいく。

「せっかく沖縄まで来たんですからねー、ちょっと島を巡ってみましょうや?」
その朝、白い軽トラックが農園の坂道をゆるやかに上ってきた。
島袋さんが運転席の窓を開け、にこやかに声をかける。
研究の一区切りがついた今、
高埜木魂の中には、ようやく“見ること”に向けられる余白が生まれていた。
彼は素直に頷き、助手席に乗り込んだ。

しばらく走ると、風景がゆるやかに変わっていく。
舗装路の端に野花が揺れ、海からの風が山の斜面を渡ってくる。
島袋さんは、ハンドルを握りながらぽつりと呟いた。
「きゅうはね、南部んかい行きましょうか。
ちょい静かなとこさぁ」
(今日はね、南部に行きましょう。
ちょっと、静かなところです)
軽トラックは坂を登り、やがて一角の駐車場に滑り込む。
高埜木魂が降り立つと、目の前にはコンクリートの慰霊塔があった。
──ひめゆりの塔。
観光シーズンを外れたその場所には、人の姿がなかった。
空は澄みわたり、ただ風だけが、淡く通り抜けていた。

塔の前に立ったとき、
高埜木魂の胸の奥で、何かがひそやかに揺れた。
風が、吹いた。
音も、香りもない。
けれど、その気配が、はっきりと“触れて”くる。
そこには、語られなかった声があった。
語られることのなかった、痛みの層があった。
誰かを守ろうとした命。
逃げずに、寄り添おうとした命。
そのひとつひとつが、いまなおこの場所に残っていた。
ふいに、胸の奥に雫が落ちた。
波紋のように、静かに広がっていく。

止水に一滴の水が落ちるように、音もなく伝わってくる──
少女たちの声。
「ここには敵も味方もありませんでした。
皆一つ。
命キレイ。」
命が、誰かのために差し出されること。
命が、どれほど真っ直ぐだったか。
その澄みきった光が、形を持たずにそこに満ちていた。
「……命、キレイやな」
気づけば、高埜木魂は、そう呟いていた。
それは、“見た目の美しさ”ではない。
磨かれた姿でもない。
命の使い方。
命の在り方。
そのすべてが、ただ静かに“美しい”という感覚だけを残していた。
その言葉が、胸の奥に静かに染み込んでいく。
善も悪も、超えていた。
誰かを裁くためでも、選ぶためでもない。
ただ──
命が、命として在るということ。
そこに、人の営みがあった。
止水が、かすかに鳴った。
応えるように、優しく、静かに。

帰り道、島袋さんがぽつりとつぶやいた。
「きゅうは、いい空やったさぁ。
高埜さん、うちなーは──ずっと待ってたんよ」
(今日は、いい空でしたねー。
高埜さん、沖縄は──ずっと、待ってたんですよ)
「……なんか、そんな気がしとったわ」
高埜木魂は、助手席で小さく笑った。
風が、しばらく車内を満たしていた。
*
午後、高埜木魂は研究室に戻った。
発酵液のその後の状況確認のため冷蔵庫の鍵を解除する。
一連の瓶が並ぶ棚──。
そこで、手が止まった。
瓶が、1本足りない。
静かに、確かに、並べてあったはずのボトルが、抜け落ちていた。
満月の夜に収穫した、あの果実を使った、最も初期の応答を得た瓶。
その1本だけが──消えていた。

目に見える痕跡は、何もなかった。
それでも、高埜木魂は確かに“触れられた気配”を感じていた。
そして、足元。
黒い繊維。
数日前、伊丹空港で見た男たちが纏っていたスーツと、よく似た質感。
(……やっぱり、繋がっとったんやな)
高埜木魂は、そっと棚の奥に手を差し入れた。
その奥から、わずかに“香りの層”が立ち上った。
誰かが、瓶に触れた。
誰かが、この部屋で“何かを動かした”。
研究ノートを開く。
ボトルナンバーの横に、一本だけ、消されたような跡。
薄く残るインク。誰かが、記録をなぞった──。
(そら、そうなるわな……)
彼は棚を閉じながら、かすかに笑った。
その声は、どこかで覚悟を決めた者のそれだった。
精霊は、沈黙していた。
止水も、何も告げない。
けれど──
彼は、すでに感じていた。
次の問いが。
次の応答が。
そして──
次の戦いが、始まる。


