ヴィウの囁きと美しき挑戦。
シーズン1 始まりのささやき
エピソード2〈崩れゆくリズム〉
朝の会議室に、プリントアウトされた資料が並んでいた。
立て直しの新企画──一週間で組み直したとは思えない完成度に、スタッフから驚き混じりの声が漏れる。

「さすがチーフですね」
「これならいけそうです」
部長もうなずき、「君ならできると思っていた」と短く言った。
ほんの数日前まで崩壊寸前だったプロジェクトは、いまや再び走り出している。
しかし、奈緒美の表情に晴れやかな色はなかった。
(立ち直った。
そう見えているんだ、みんなには)
奈緒美は頬に微笑みをつくった。だが、その内側で別の声が響いていた。
(でも…本当にこれでいいの?)
アイデアは理屈として正しい。データも裏付けている。
けれど、胸の奥で何かがしっくり来ない。
*
「ランチどう?」
昼休み、スマホにメッセージが入った。
送り主はゆう子。奈緒美と同い年で、同じ会社の別部署にいる親友だ。

会社から歩いて数分、いつもの「カフェ・セレニタ」。
黄色い壁にグリーンの窓枠、外にはツタや花がからまり、テラス席には小さな鉄の丸テーブル。
晴れた日には光を浴びて柔らかな陰影を作り、街角の一角を穏やかに照らしている。
中に入ると木のテーブルと椅子、壁には古い絵画や洋書が並び、奥では豆を挽く音。
深煎りの香りがふんわりと漂い、オフィスの喧噪から切り離された別世界だった。
窓際の席に座ったゆう子は、メニューを閉じると弾む声で言った。
「ねぇ、聞いて!
新しい彼氏ができたの!」
奈緒美は少し驚き、目を瞬いた。
「そうなの?
どんな人?」

「カナダ人なの。
こっちじゃ考えないようなことを普通に言うのよ。
それがちょっと面白くて」
「カナダ人…」
その単語だけが、奈緒美の胸に引っかかった。意味もなく、遠い未来を連想させる。
「で、奈緒美。
最近、肌がちょっと荒れてない?」
「わかる?」
「わかるよ。
ファンデで隠しても、目の下の疲れは隠せないもん」
ゆう子は紙ナプキンでカップを拭いながら、小さな声で付け加えた。
「無理を積み重ねても、いいものはできないよ」
「……わかってる」
わかっている。けれど止まれない。
無理は承知。それでも、止まった瞬間、全体が崩れてしまう気がするから。
*
午後の会議は時間通りに進み、反応も悪くない。
スタッフの一人が「これなら勝てますね」と言う。
奈緒美は笑みを返しながら、心の奥に小さなざらつきを覚えた。
(勝てる? 本当に?)
(私、何と戦っているのかな……)
ようやく仕事の段取りは整い始めた。
だが家庭のリズムは、逆に崩れていた。
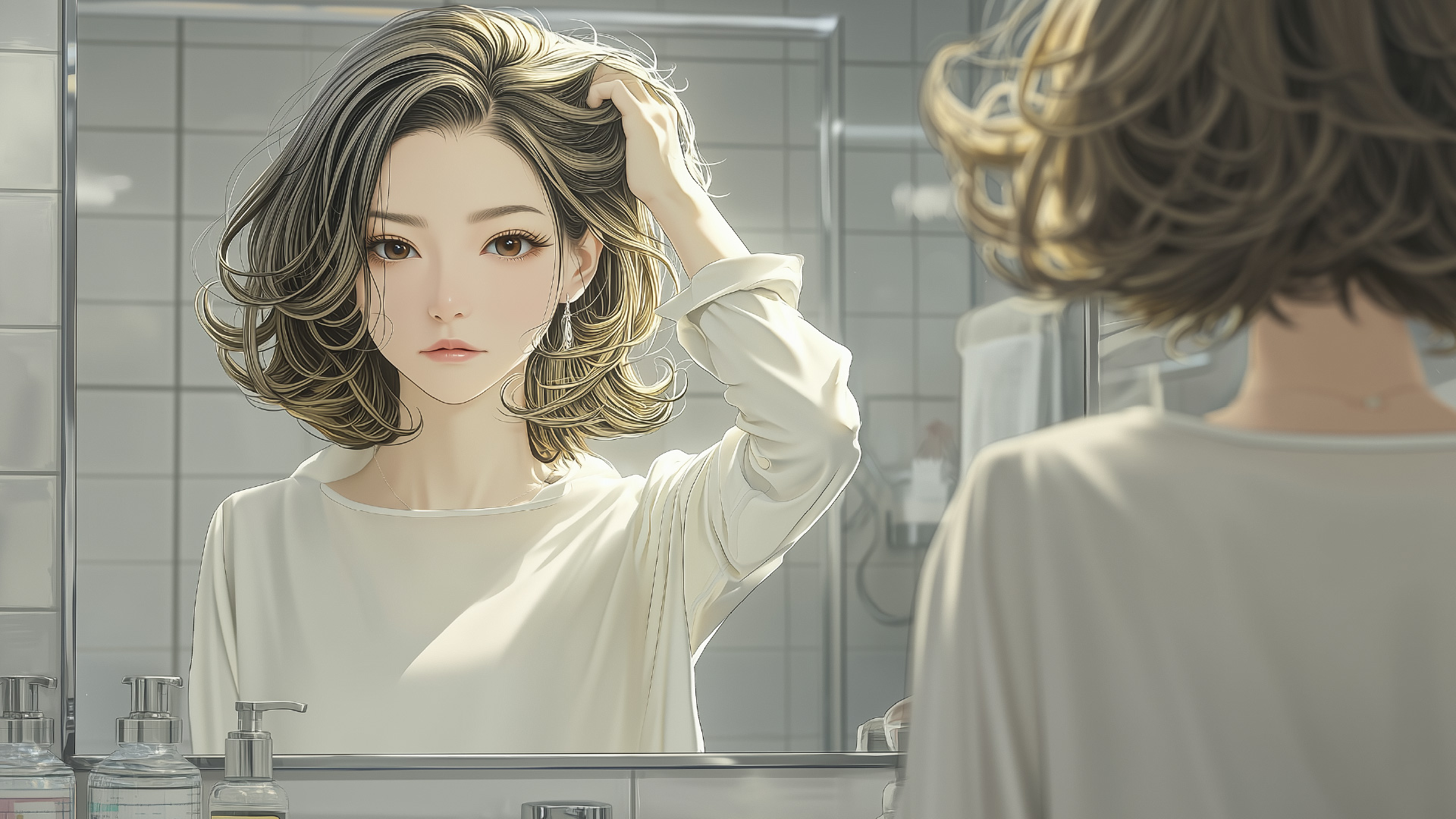
会議の後、化粧直しのサニタリースペースで、奈緒美はふと、今朝の自宅のリビングを思い出した。
健一とは「行ってらっしゃい」「おやすみ」以外の会話がほとんどなくなり、
子どもたちの声を聞く時間は減り、肌は日ごとに荒れていく。
鏡を見るのが怖かった。
(このままでいいの?)
その問いが、企画のことなのか、私生活のことなのか、境界が曖昧になっていく。
*
夕方、祐輔が分厚いファイルを抱えて近づいてきた。
「チーフ、数字の差し込み終わりました」
「助かるわ。
今回の骨子、祐輔くんがまとめてくれたおかげで形になったのよ。
ありがと」
「いえ、まだまだです。
…でも、任せてもらえて嬉しかったです」
祐輔は少し照れたように笑い、続けた。
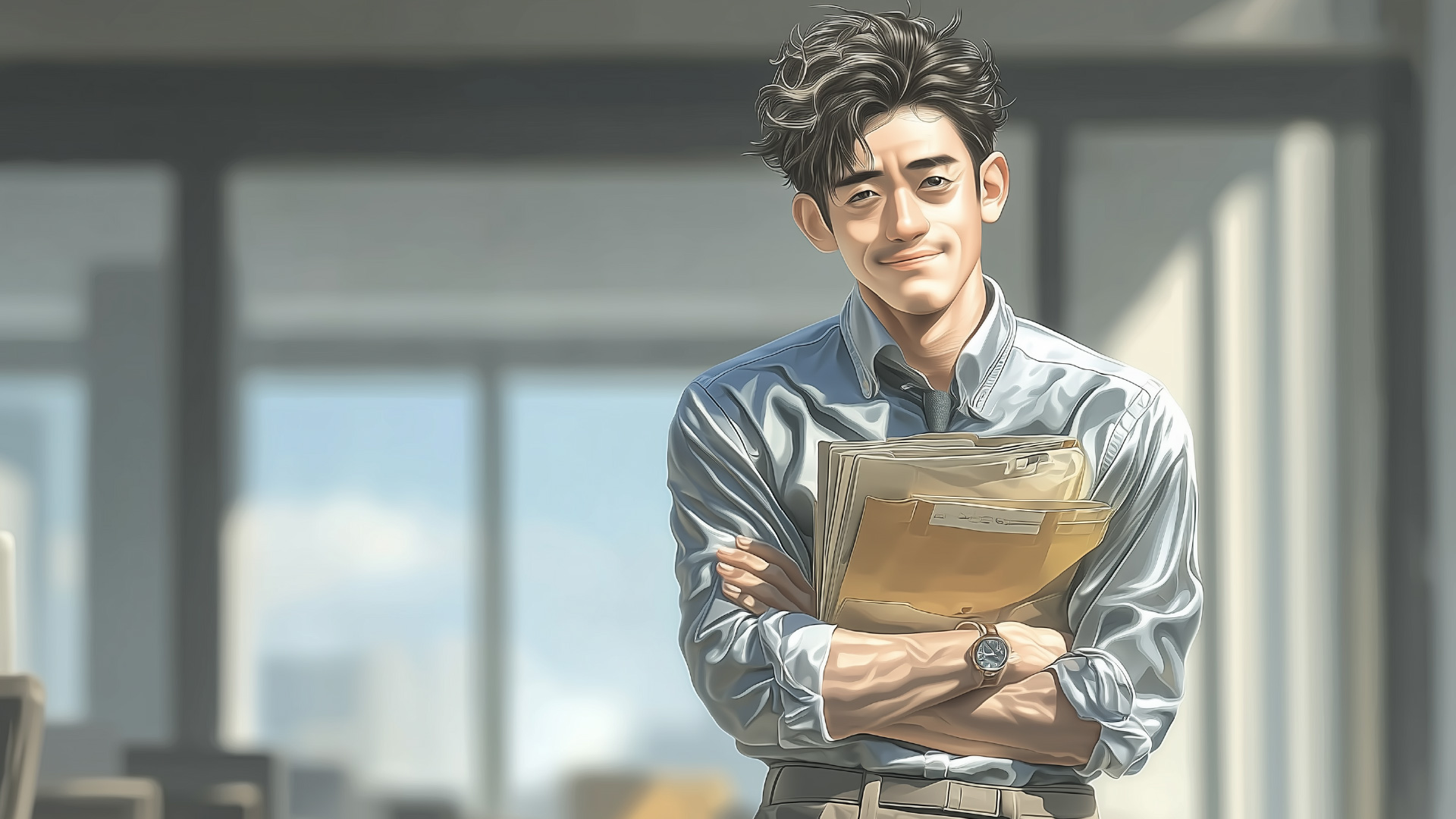
「ぼく、この会社、営業で入ったんですけど……本当はクリエイティブやりたくて。
あ、いや、前はそんなこと思ってただけで」
言葉を打ち消すように笑ってから、気を取り直すように声を落とした。
「昨日報告したログの件、特に大きな問題はなさそうなんですけど……なんとなく引っかかる感じがあって」
「気になるなら見ておいて。
何かあれば教えて」
「了解です」
ほんの一瞬のやり取りだったが、奈緒美は若い彼の素直な熱を感じた。
それは、かつて自分が抱いていた衝動にも似ていた。
*

終電間際に帰宅すると、リビングは暗かった。
テーブルの上には子どもたちのプリントやお菓子の袋、読みかけの雑誌が散らばったまま残っている。
今は誰もいないテーブルを、奈緒美はしばらく立ち尽くして見つめた。
そこに、彼女のいない時間の気配がまだ残っていた。
洗面所の鏡に映った顔は、朝よりさらに色を失っている。
肌は乾き、目の下のクマは濃く沈んでいた。
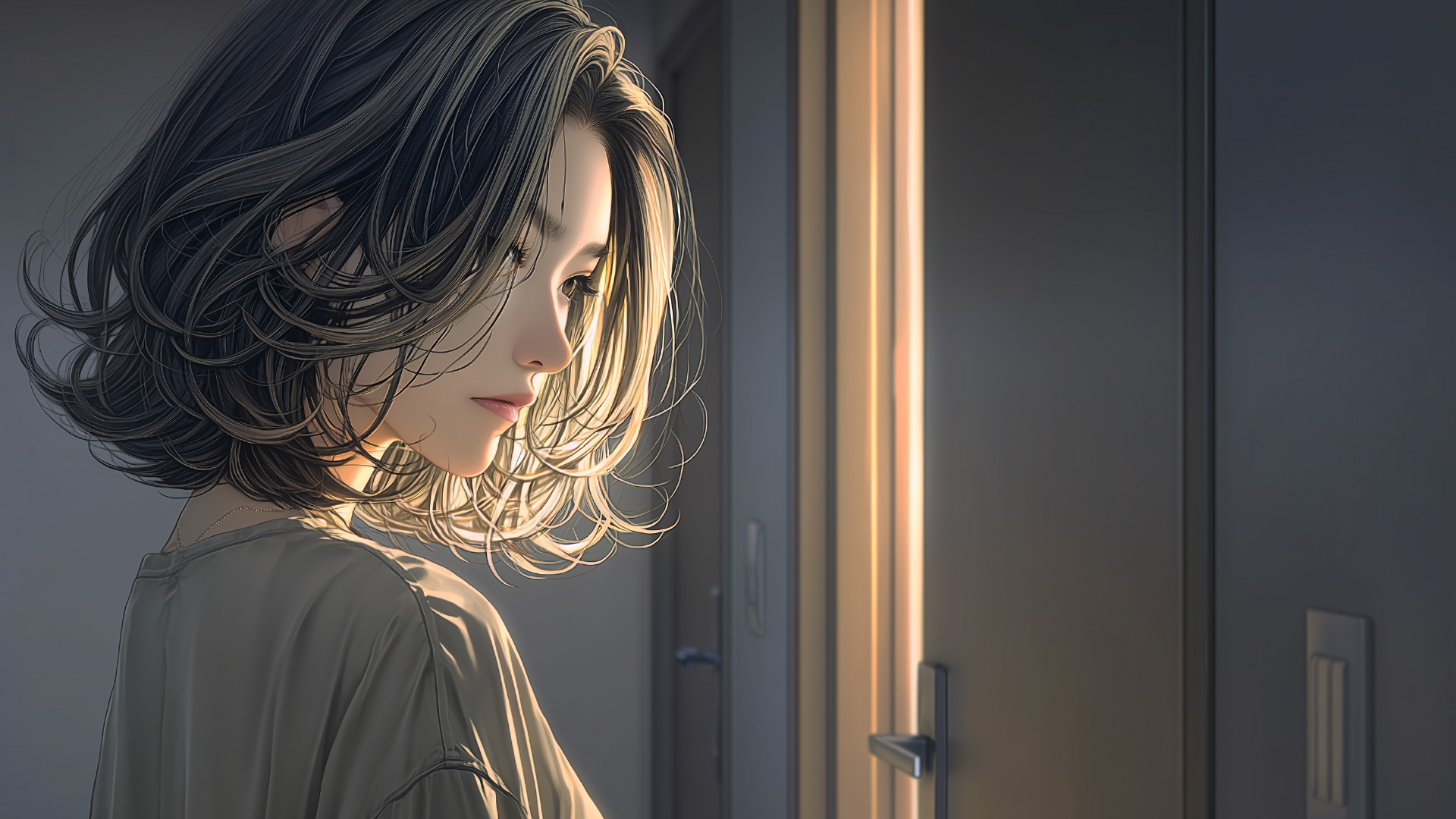
奥の愛莉の部屋のドアの隙間から、かすかな灯りが漏れていた。
扉をノックして「早く寝なさい」と言おうとしたが、唇が動かなかった。
言葉を飲み込んだまま、背を向ける。
そのとき、スマホが震えた。
画面に浮かぶ見覚えのある言葉。
──ヴィウの囁きに耳を傾けて。
キレイはあなたの中にある。
(何よ、これ……)

眉間に力が入り、舌打ちしそうになる。
癒す言葉のはずなのに、今はただ苛立ちを誘うだけだった。
奈緒美は目を閉じ、深く息を吐いた。
企画は立ち直りつつある。
でも、自分の心と生活のリズムは、確実に崩れかけている。
(何かが違う。
このままでいいの?)
その問いだけが、夜の静けさに残った。

